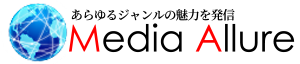2025年10月6日、京都大学および大阪大学名誉教授・特任教授の 坂口志文(さかぐち しもん) 氏が、ノーベル生理学・医学賞 を受賞したことが発表されました。
今回の受賞は、日本の医学・生命科学研究にとっても画期的な出来事です。本稿では、坂口氏の歩みと功績、そしてこの受賞が持つ意味を丁寧に紐解いていきます。
坂口志文とは:人物像・経歴
生年月日・出身地
坂口志文氏は 1951年1月19日生まれ、滋賀県(東浅井郡、長浜市)出身です。
学歴・研究拠点
京都大学にて医学博士号を取得後、米国の Johns Hopkins 大学や Stanford 大学でポストドクトラル研究を経験。
帰国後は京都大学、そして大阪大学の免疫学フロンティア研究センター(IFReC)などで研究を重ねられています。
これまでの受賞・栄誉
- Gairdner 国際賞(Gairdner Foundation Award)など国際的な賞を受賞
- クラフォード賞(Crafoord Prize) 2017年受賞。リスト
- 文化勲章(2019年)を受章
- ロバート・コッホ賞(Robert Koch Prize)
これらの受賞歴は、坂口氏が長年にわたって免疫研究の最前線で貢献してきた証といえます。
受賞理由:制御性T細胞と末梢免疫寛容
ノーベル財団は、2025年のノーベル生理学・医学賞を、メアリー・ブランコウ氏(Mary E. Brunkow)、フレッド・ラムズデル氏(Fred Ramsdell)、および 坂口志文氏 の3名に授与すると発表しました。
制御性T細胞(Treg 細胞)とは何か
制御性T細胞(Regulatory T cell, 略して Treg 細胞)は、過剰な免疫反応を抑制し、自己免疫反応を制御する働きを持つ免疫細胞の一種です。坂口氏の研究は、この細胞群の存在を示すとともに、その分子メカニズムを明らかにしました。
これまで、免疫応答を“攻撃”と“抑制”のバランスという観点から理解するモデルはありましたが、具体的な抑制機構の中核となる細胞が明確に示されたのは坂口氏らの業績が先駆と言えます。
まとめ
坂口志文氏による制御性T細胞の発見は、免疫学の常識を根底から覆すものであり、人類の健康と生命科学の未来に大きな道を開きました。
今回のノーベル生理学・医学賞の受賞は、長年の研究努力と科学への信念が世界に認められた証といえるでしょう。
今後、この成果が自己免疫疾患やがん、移植医療などの治療法へとつながることで、多くの人々の命を救う礎となることが期待されます。